Events
イベント
2025 CHAIN Summer School
2025年度 CHAINサマースクール:「生命と言語進化の構成論」

CHAINでは「意識・自己・社会性・合理性」といったテーマに対して哲学・神経科学・AI研究の融合した学際的教育プログラムを北大の大学院生に向けて提供しています。その中で夏と冬に開催されるサマースクール・ウインタースクールでは外部講師をお招きし、受講生に最先端の知見に触れ、学際的議論を行う場を提供しています。
2025年度のサマースクールはテーマを「生命と言語進化の構成論」と題して、以下の先生方をお呼びして、講義・議論を行います。(敬称略)
- 特別講演:岡ノ谷 一夫 (帝京大学 教授,東京大学名誉教授・客員教授)
- 講師1: 橋本 敬 (北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授)
- 講師2: 岡 瑞起 (千葉工業大学 変革センター 主席研究員,IPA未踏IT人材発掘・育成事業PM,株式会社ConnectSphere代表取締役)
岡ノ谷一夫先生は東京大学大学院総合文化研究科の元教授で、動物行動学、特に鳥類の歌学習や言語進化の研究で国際的に著名な研究者です。ジュウシマツやコシジロキンパラなどの鳴禽類を用いて、動物の音声コミュニケーションと人間の言語の進化的関係を解明する研究を長年にわたって行ってきました。現在は帝京大学先端総合研究機構の特任教授として研究を続けており、動物の認知能力や社会行動に関する多くの重要な発見を発表しています。
また、お二人の講師はともに、長年にわたり人工生命の研究に携わってこられました。
橋本敬先生は、「コード(テープ)と装置(マシン)の相互作用による自己複製・進化システム」の研究を通じて、遺伝情報とそれを読み解く仕組みが共進化し、安定した構造を形成する過程を明らかにされました。最近では、言語進化やコミュニケーションの生成、社会制度の形成といった現象を対象に、複雑系の視点から研究を展開されています。
岡瑞起先生は、人工生命が内包する「創発性」「身体性」「オープンエンド進化」といった本質的課題に対し、LLMなどの最新AI技術を取り入れた実践的なソフトALifeの構築と、社会実装を見据えたコミュニティデザインの両面から研究を進められています。また、人工生命に関する著作もあり、『ALIFE | 人工生命 ―より生命的なAIへ』や『作って動かすALife ―実装を通した人工生命モデル理論入門』は、人工生命研究の優れた入門書として広く読まれています。
【最新の情報については、随時更新いたします。】
Seminar1

Lecturer
1.「言語進化の構成論:進化・創発の構成から人間本性に迫る」2.「共創言語進化:再帰性と意図共有の統合」
Abstract:
言語は人間を人間たらしめる最も重要な能力の一つである。われわれは、この言語をどのようにして手にし、それはいかにして現在のような姿になったのか。この言語の起源・進化の問いは、生命や宇宙の起源と並んで、人類誕生以来問われてきたであろう、われわれ自身と世界の存在に関わる根源的な問いである。この根源的な問いに対して20世紀終わりごろから科学的探究が本格化している。
しかし、言語の起源・進化の直接的証拠を得ることは困難であるため、構成論的アプローチ—、すなわち作って動かすことを通して理解する手法—が重要となる。構成論とは、対象現象の理論的分析だけでなく、仮説に基づいて実際にシステムを構築し動作させることで理解を深める研究手法である。観察的・記述的アプローチでは捉えきれない動的なメカニズムや創発的プロセスを、シミュレーション、実験、人工システム構築を通じて明らかにする。この方法は、実験的な検証、創発的な発見、そして概念的探究の観点で効果的だと考えられる。言語進化研究においてこのアプローチが有効なのは、言語が複雑な相互作用から創発する動的システムであり、その進化過程の一端を再現・検証できるからである。
この2回の講義では、言語を進化の観点から捉え直し、構成論的研究によってその仕組みと人間的特質について考察を深めたい。すなわち、言語の起源・進化自体を知ることは最終目的なのではなく、進化的観点から言語を見ることで、言語により特徴づけられる人間の本性を、そして、われわれ自身について探究したい。
言語進化の構成論では、あらゆる個別言語が普遍的に持つ基本的な性質に着目し、その創発を構成することを試みる。第1回の講義では、言語進化の構成論研究をいくつか採り上げ、その特徴や射程を示す。まず、記号を用いたコミュニケーションシステムの創発に関する研究を紹介する。Naming Gameや実験記号論の研究により、エージェント間の相互作用から記号システムが自己組織するプロセスを観察できる。続いて、人間の言語を特徴づける要素の一つ「合成性」を取り上げる。これは、複合体(文など)の意味がその構成要素(単語など)の意味と組み合わせ方で決まるという性質であり、有限の語彙と規則から無限の表現を生み出す基盤となる。合成性は繰り返し学習(iterated learning)によって自然に創発し得ることが、多様な方法で確認されている。講義では繰り返し学習がもたらす利点と限界を具体例を交えて考える。そして最後に、人間の言語が持つ最も特徴的な性質の一つである「超越性」――いまここから離れた事象について語れる能力――について、実験記号論の成果をもとに議論する。
共創言語進化:再帰性と意図共有の統合
言語がコミュニケーションに用いられることは明らかだが、言語がコミュニケーションのためだけに進化したと考える必要はない。むしろ言語は、思考を精緻化し概念を構築・創造することに極めて有効である。この観点から言語を見ると、言語文が階層的構造をなし、その構造が意味を持つ要素の再帰的な組み合わせにより作られるという、その本質的特徴が浮かび上がる。ここで言う再帰性は、「AがBについて考えていることをCが知っている、ということをDが...」という入れ子構造ではない。ある操作をその操作の結果に対して適用する認知的メカニズムを指す。階乗(N!)の計算アルゴリズムが再帰の典型例である。この再帰的処理能力が、上記の入れ子構造も含む複雑な階層構造を持つ言語表現、そして、言語表現が表す概念構造の構築を可能にしている。
また、人間のコミュニケーションは意図の共有を基盤として成り立っていると考えられる。われわれが他者の行動を理解する際、その背後にある意図(理由)を推測することで納得を得る。この意図理解は他者行動の予測を可能にする高次の認知能力である。
このように、人間の言語コミュニケーションは、階層性を生み出す再帰性と他者との意図共有の2つが統合されている点が、他の動物の思考とコミュニケーションにない特異的な点である。このような観点から言語の起源・進化を探究する企てが「共創言語進化」である。第2回の講義ではこの共創言語進化の構成論的研究を紹介する。
共創言語進化の核心的問題は、再帰性と意図共有がいかにして統合されているかである。本講義では、意図共有の基盤に再帰性があるという統合モデルを提示する。
具体的には、他者意図の推測はアブダクション(仮説推論)によってなされ、この仮説生成過程に再帰性が関与しているという説を検討する。アブダクションは、観察された現象を説明する最適な仮説を生成・選択するプロセスである。再帰的な概念操作により多様な仮説空間を探索できるようになる可能性がある。これらの理論的仮説を検証するための実証的探究を題材に、再帰性と意図共有の統合や人間の言語・思考・コミュニケーションの特質について議論したい。
講師紹介
橋本敬(北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科教授)
1996年東京大学大学院院総合文化研究科博士後期課程修了.博士(学術).
理化学研究所脳科学総合研究センター基礎科学特別研究員.
北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授を経て,2009年より同教授.
その間、SONY Computer Science Lab.- Paris,エディンバラ大学言語進化計算グループ,Telecom ParisTechネットワーク・計算機科学部にて客員研究員として在外研究.
複雑系科学の観点から主に言語・コミュニケーション・社会制度を対象に知識の創造・共有・活用を探究する知識科学の研究に従事。
Seminar2

Lecturer
AIとの共創:Open-endednessとOrganic Alignmentが拓く未来 1・2
Abstract:
講師紹介
千葉工業大学 変革センター 主席研究員 / 博士(工学) / IPA未踏IT人材発掘・育成事業PM / 株式会社ConnectSphere代表取締役
Open-EndednessやProbabilistic Computingをテーマとする人工生命(ALife)研究に従事し、人間とAIが共創(co-creation)する未来社会の創出を目指している。特に、創造的でありながら安全性を兼ね備えたAIの開発を通じて、イノベーション促進や新たなコンテンツ創出に取り組む。大学での研究をベースに、社会実装にも力を入れる。著書に『ALIFE | 人工生命 ―より生命的なAIへ』『作って動かすALife ―実装を通した人工生命モデル理論入門』がある。
Seminar3
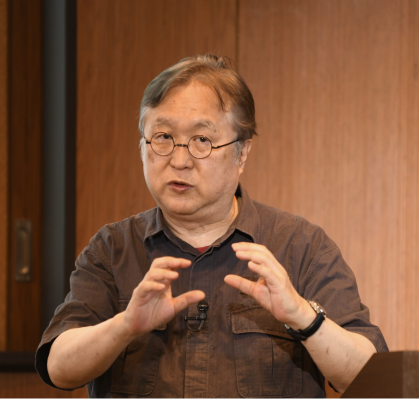
Lecturer
1.「コミュニケーション行動から探る動物の心的世界」 2.「コミュニケーション行動から探る意識の進化」
Abstract:
コミュニケーションを「送信者が発する信号により受信者の行動変容が起こり、そのことで長期的には送信者が利益を得るような動物どうしの相互作用」と定義する。生物心理学とは、「生物学的な手法を活用して動物の心的体験を推測する学問」である。言語はコミュニケーションの手段の1つであり、コミュニケーションと同義ではない。コミュニケーションは複数個体がいて発生することだが、言語は単独でも思考の手段として用いられる。本講演では、本研究室で行われた動物のコミュニケーション実験の事例を7つ(社会的促進、情動伝染、利他行動、他者操作、話者交代、時間知覚、メタ認知)紹介し、動物の心的体験について考えてみる。
これらの事例から、動物たちの心の世界が垣間見える。コミュニケーションの定義自体は操作的であるが、実際には心的過程が存在すると考えるのに十分な行動が多い。こうした観察事例を積み重ね、行動と相関する神経活動を記録することで、動物の心の世界がどう構成されるのか、理解が進むであろう。
コミュニケーション行動から探る意識の進化
主観的体験としての自己意識はどのように形成されるのか。コミュニケーションが最重要な手がかりだと私は考える。コミュニケーションを理解するには、他者の模倣、他者への共感、そしてそれらによる報酬の履歴が重要であり、これらの要素は現代の生物心理学的手法により解明可能である。その上で「他者の行動からその内部モデルを構成すること、そしてそれを自分自身に振り向けることで自己意識が生まれる」という仮説を提案する。
現代の意識研究の限界は、その起源を考えてこなかったことにある。生物とは生存し増殖するものだ。大切なことはまず捕食者に適切に対応する敵対的なコミュニケーションだ。さらに遺伝子の交雑により増殖するような生物になると、他個体との親和的なコミュニケーションが生存を左右する。群れが持続的になると、互恵性や利他性も生じてくる。この段階では、親和的なコミュニケーションの意義はいっそう大きい。敵や仲間の行動モデルの形成が必要になり、そこで必要とされる情報処理が情報的意識として発生したと考えてみよう。さらに、他者のモデルを構成する仕組みをもって、自分自身の行動予測をする自己のモデルを持つことで、可能な選択肢のうち特定の行動を選択し他の行動を抑制する機能が発生するであろう。これらの自己モニター機能が、体験的意識を形成するようになったのであろう。このような枠組みを設定すると、コミュニケーションを通して情報的意識と体験的意識を連続的に考えることが可能になる。
講師紹介
岡ノ谷一夫
(帝京大学先端総合研究機構・特任教授/東京大学大学院総合文化研究科・客員教授)
略歴
1983年 3月 慶応義塾大学文学部卒
1989年 5月 米国メリーランド大学大学院心理学研究科修了、Ph.D.
1994年 3月 千葉大学文学部助教授
2004年 4月 理化学研究所チームリーダー
2010年 7月 東京大学大学院総合文化研究科教授
2022年 4月 帝京大学先端総合研究機構教授
2025年 4月 帝京大学先端総合研究機構特任教授、現在に至る
書籍
著書
さえずり言語起源論(2010年 岩波書店)
言葉はなぜ生まれたのか(2010年 文藝春秋社)
つながりの進化生物学(2013年 朝日出版社)
脳に心が読めるか(2017年 青土社)
人間の心が分からなかった俺が、動物心理学者になるまで(2025年9月 新潮社)